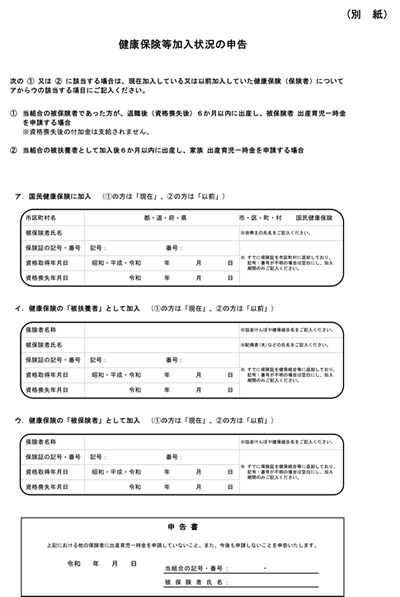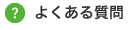出産したとき
概要
出産育児一時金・家族出産育児一時金
被保険者や被扶養者である家族が出産したときに、その出産に要した費用に対しての給付と出生児の育成に対する給付として、出産育児一時金(家族出産育児一時金)が支給されます。
現在、出産に係る費用の窓口負担軽減のために、「直接支払制度」と「受取代理制度」が実施されています。
提出書類
直接支払制度
被保険者が医療機関等との間に、出産育児一時金等の支給申請と受け取りに係る代理契約を締結し、その医療機関が被保険者に代わって出産育児一時金等の額を限度として出産育児一時金等を受け取るものです。
出産費用が50万円(産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産)または48.8万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産、また加入していても在胎週数22週未満の出産の場合)に満たないときの差額及び出産育児一時金付加金等の請求方法は、次のとおりです。
出産育児一時金差額・付加金請求書
当組合から被保険者に支給決定通知書を送付する際に『出産育児一時金差額・付加金請求書』を同封いたします。必要事項を記載し、記名・捺印のうえ、当組合まで請求書を返送してください。
| 必要書類 |
|
|---|---|
| 支給額 | 出産育児一時金等に満たないときの差額と付加金(1児につき被保険者26,000円、被扶養者16,000円)が支給されます。 |
出産育児一時金差額(内払)・付加金支払依頼書
当組合から送付する『出産育児一時金差額・付加金請求書』で給付金を受取るには出産から2~3ヶ月かかることから、『出産育児一時金差額・付加金請求書』を待たずに、事前に被保険者から出産育児一時金等の差額及び出産育児一時金付加金等を請求することができます。
| 必要書類 | |
|---|---|
| 添付書類 |
|
| 支給額 | 出産育児一時金等に満たないときの差額と付加金(1児につき被保険者26,000円、被扶養者16,000円)が支給されます。 |
受取代理制度
被保険者が医療機関を受取代理人として出産育児一時金等を事前に健康保険組合へ申請し、医療機関が被保険者に対して請求する出産費用の額(請求額が出産育児一時金として支給される額を上回るときは出産育児一時金の額)を限度として、医療機関が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取るものです。
受取代理制度を導入することを厚生労働省に届け出た医療機関が対象となります。
出産育児一時金・付加金請求書(受取代理用)
受取代理制度を導入する医療機関において出産を予定している被保険者または被扶養者で、出産予定日まで2ヶ月以内の時、申請書に必要事項(受取代理人となる医療機関による記名・捺印等を含む。)を記載のうえ提出してください。
| 必要書類 | |
|---|---|
| 支給額 | 出産育児一時金等に満たないときの差額と付加金(1児につき被保険者26,000円、被扶養者16,000円)が支給されます。 |
受取代理申請の取り下げ
予定していた医療機関以外で出産することとなった場合、速やかに取下げ申請を行ってください。
また、新たに出産することとなった医療機関において受取代理制度を利用する場合には、改めて受取代理申請書を作成し提出する必要があります。
| 必要書類 |
|---|
受取代理人の予定外の変更
救急搬送などにより、予定していた医療機関以外で出産することとなった場合であって、新たな医療機関において受取代理制度を利用する場合など、受取代理人の変更に伴う申請取下げ及び再申請の時間的余裕がない場合には、受取代理人の変更届に必要事項(変更前及び変更後の受取代理人である医療機関による記名・捺印等を含む。)を記載の上、新たに受取代理人となる医療機関を通じて提出することになります。
直接支払制度または受取代理制度を利用しない場合
直接支払制度または受取代理制度を利用せず、従来の方法で出産育児一時金等の請求を行う場合。
| 必要書類 | |
|---|---|
| 添付書類 |
|
| 支給額 | 出産育児一時金、家族出産育児一時金ともに、1児につき500,000円が支給されます。産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産された場合や、産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合であっても、在胎週数22週未満の出産であるときは488,000円が支給されます。 付加金については1児につき被保険者26,000円、被扶養者16,000円が支給されます。 |
留意事項
出産育児一時金および付加金は、出生児1児ごとに支給され、双生児の場合は、2児分支給されます。
なお、出産については妊娠4カ月(85日)以後の出産(早産)のほか、死産(流産)も含まれます。
育児休業中の保険料免除に
- ※下記、①又は②に該当する方が請求する場合は、請求書の他(別紙)「健康保険等加入状況の申告」を記入してください。
(別紙)